上流には不気味な柳屋敷
 中渋谷村は、江戸の外れにある。
中渋谷村は、江戸の外れにある。
ほとんどは田んぼと畑になっているが、大山道の途中にある二つの坂道──宮益坂と道玄坂のあたりに小さな町ができていて、それぞれ渋谷宮益町、渋谷道玄坂町と名付けられていた。
その宮益町の、とある長屋の子どもたちが、このところぴたりと食欲が絶えていた。
このあいだまでは、飯どきになれば、
「おっかあ、腹減った」
の声がうるさいほどだったのである。
それがなにも言わない。三杯食べていた飯を一杯しか食べない。
長屋のおかみさんの一人が怒鳴った。
「お前、どこかでなんか食っているのかい? 草の実だのには毒があったりするから、やたらと食べるんじゃないよ!」
叱られて、正直な子どもがついに白状した。
「川に流れて来る、白くて細いうどんを食っているんだよ」
「細いうどんが流れて来るだって?」
「うん。すごくうまいよ」
「毒かもしれないのに、変なものを拾い食いするんじゃない」
「わかった。もう、食べない」
と、子どもは素直に謝った。
だが、不思議ではないか。なぜ、川にそんなものが流れて来るのか。
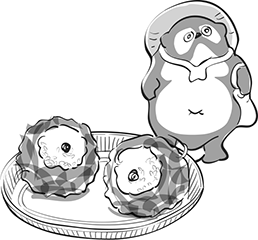 「へえ、これか」
「へえ、これか」
一目見て、魚之進は感心した。
いかにもたぬき寿司なのである。
酢飯がおにぎりより真ん丸く握られている。それにかつおぶしをいっぱいくっつけているのだが、正面だけは白い酢飯が見えるようにしてある。そのかたちがまさにたぬきの腹に見えるのである。
しかも、真ん中に細かく切った紅い梅干しのひとかけらが載っている。これはへそに見立ててあるのだ。
「見えるな」
と、魚之進は言った。
「ええ、たぬきに見えます」
 「飴に名前なんかあったんですか?」
「飴に名前なんかあったんですか?」
「ああ。ちくび飴はまずいよな」
「ちくび飴……ちくびって?」
「女のここについてるやつだよ」
と、赤塚は自分の胸を指差した。
「…………」
「お前、なに、顔を赤くさせてるんだ?」
「いや、べつに」
そういうものとはまったく気づかなかった。
「風紀を紊乱させているよな」
「そ、それは……」
「お前、舐めたのか」
「舐めたといっても、そういう厭らしい気持ちで舐めたわけではありませんよ」
「別に厭らしい気持ちで舐めたっていいんだぞ」
「…………」
「娘が三人いただろう?」
「ええ」
「それぞれの乳首と同じ色かたちをしているらしいんだ」
赤塚は嬉しそうな顔で言った。
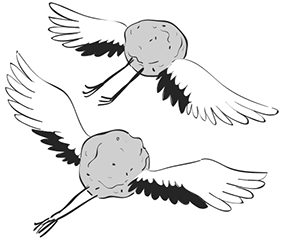 「そういや、つるもどきをつくった坊主がいるらしぜ」
「そういや、つるもどきをつくった坊主がいるらしぜ」
「つるもどき?」
「ああ、がんもどきじゃねえ。つるもどき」
「だが、鶴は禁漁だぞ。食ったら駄目だろう」
将軍の好物らしい鶴を、民は獲って食ったりしてはいけないのだ。
「だから、もどきにしたんだろうが」
「うまいのかね」
「恐ろしくうまいらしいぜ」
この言葉に魚之進と麻次は顔を見合わせた。
恐ろしくうまいもの。
禁漁の鶴に似た味。
しかも、仏の道に通じる精進料理。


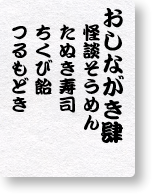
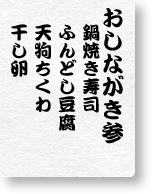
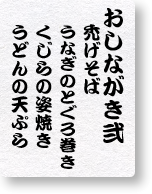
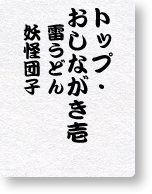
![[書影]講談社文庫](content/images/ajimi/book_4.png)
![[書影]講談社文庫](content/images/ajimi/book_1.png)
![[書影]講談社文庫](content/images/ajimi/book_2.png)
![[書影]講談社文庫](content/images/ajimi/book_3.png)