葉室麟氏が、小説を書くときはいつもどこかで自分の過去と向かい合っているという。人間を長く生きていると、あのとき自分がしたことはあれで良かったのかとか、あのときのあの人の気持ちはどうだったんだろうとか、心残りになる疑問がどんどん積み重なってくる。死ぬまでその回答は恐らく得られない、でもそのときの自分を見直したい。はたしてあのときの自分にどういう意味があったのだろうかと、葉室氏は小説を通して熟考する。黒島藩シリーズは人生を経た大人が、過去と痛切な思いで対峙する小説である。

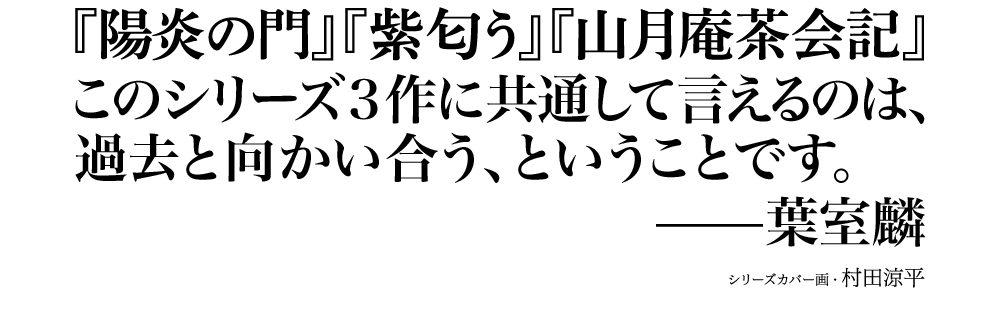
葉室麟氏が、小説を書くときはいつもどこかで自分の過去と向かい合っているという。人間を長く生きていると、あのとき自分がしたことはあれで良かったのかとか、あのときのあの人の気持ちはどうだったんだろうとか、心残りになる疑問がどんどん積み重なってくる。死ぬまでその回答は恐らく得られない、でもそのときの自分を見直したい。はたしてあのときの自分にどういう意味があったのだろうかと、葉室氏は小説を通して熟考する。黒島藩シリーズは人生を経た大人が、過去と痛切な思いで対峙する小説である。
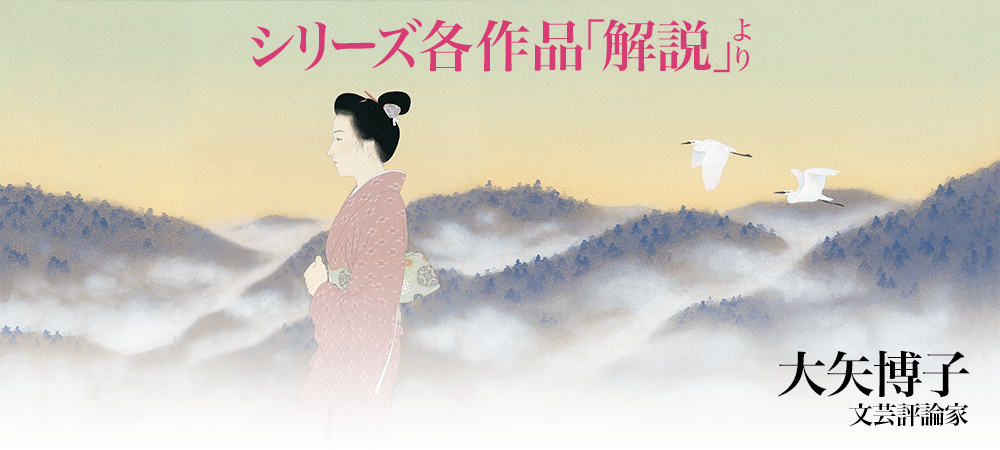
人は誰しも過ちを犯す。人としての真価が問われるのは、その過ちを認められるかどうか、そしてその過ちにどう対処するかだ。
ミステリとしての趣向も本書の大きな魅力だが、真犯人がわかってから──つまり過去の自分の判断が間違っていたことを主水が知ってから、彼が何を考え、どんな行動をとるかにこそ、注目されたい。
従来の葉室作品には清廉潔白な主人公が多かったが、本書は違う。(本書の主人公)主水には出世への強い憧れがあったし、綱四郎を断罪したときライバルを蹴落としたという思いも皆無ではなかった。だからなおさら、自分の行為は正しいと思いたかった。過ちであることを恐れた。主水は実に人間的なのだ。
物語が大きく動くのは、澪と笙平が潜んでいた宿に蔵太が現れてからだ。蔵太は澪とともに笙平を助けるため、力を尽くす。妻が結婚前に関係を持った男と知っていながら、である。
読者は│特に女性読者は、蔵太と笙平の格の違いに早々に気づくだろう。だからこそ、揺れる澪にヤキモキさせられる。目を覚ませ、と言いたくなる。だが同時に、理性ではわかっていてもどうにもできないことがある、という心情も理解できるからたまらない。
また、3人の逃避行はそれ自体がとてもサスペンスフルで、彼らを狙う仇敵との対決は剣豪小説さながらの読み応えだ。細かな伏線が効いてくる構成もさすがと言っていい。一方、炭焼き小屋で複雑な三角関係の3人が一夜を明かす場面は、剣戟場面とはまた違った緊迫感がある。
澪の気持ちの揺れというメンタルな要素と、追っ手からの逃亡や対決というアクション。緩急の効いた展開は読者を飽きさせることなく、目が離せない。
大きな読みどころがふたつある。ひとつは次第に明らかになっていく過去の事件の真相だ。(主人公)靭負の茶席に関係者が順にやってくるという構成がいい。かつて柏木派だった部下や、(16年前に死んだ主人公・靭負の妻)藤尾と同じ宴席に出た元江戸藩邸の老女、当時の藩政に強い影響力のあった影のフィクサー、当時の家老の息子などなど。探偵のもとに証人(もしくは容疑者)が訪れ、事情聴取が行われるようなものだ。
つまり本書は〈証言〉によって構成されるミステリなのである。彼らが語る〈新証言〉のひとつひとつに驚きがあり、次第に真実へと肉薄していくその過程にはドキドキする。千佳の実父・又兵衛がコミックリリーフとして場を和ませてくれるという緩急も完璧。その先に、容疑者を集めて「犯人はお前だ!」的なクライマックスがあるのだからたまらない。実に上手く構成されているのだ。1回の茶席を1話にした連続ドラマにしたいくらいである。