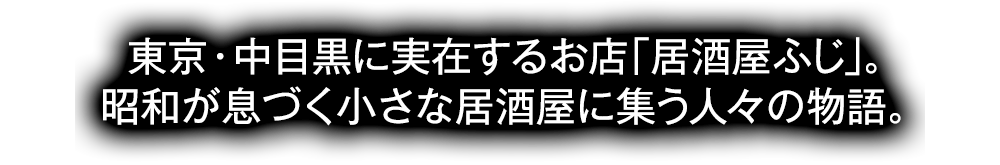── それはすごい。これまで1日も欠かさずに実践されてきたんですか。
栗山 はい、1日も欠かさずに。
── なんかヒンドゥー教の苦行みたいですね(笑)。
栗山 いや、苦しいことなんてないですよ。好きなんですから、むしろ楽しい。世のなか自分以外はぜんぶ他人で、十人いれば十通りの生き方や考え方があるわけで、まったく同じなんてことは絶対にない。必ず何かしらの発見があるんです。こんな面白いことはない、やめられませんよ、ふふふ。
逆に言えばAさんとBさんが同じことをしゃべったとします。でもこれまで百人と話してきたAさんと、百万人と話してきたBさんでは、発せられた言葉の質量というものがまるっきり違うと思うんですよね。
それから僕ね、嫌いな言葉が三つあって、それは「人見知り」「不器用」「口下手」。自己紹介で、たとえば「わたし、人見知りなんで」とか「自分、不器用ですから」とかいうでしょ。これって「だからあなたとコミュニケートしたくありません」って意味が裏に隠されているわけで、拒否の言葉ですよね。そんなの聞くとなんか切なくなる。おしゃべりすることで人を好きになるかもしれないし、器用になれるかもしれない。そんなチャンスをみすみす手ばなしているようで残念でならない。自分はこうだってキメつけてカッコつけてんじゃねーって(笑)。
── 自分と異なる個性や人生を知るということを、多くの人は読書を通じて体験します。栗山さんはそれをリアルな人間関係の上で行ってきたということなんですね。栗山作品の面白さの理由がわかったような気がします。さて、デビュー作でこのたび文庫化される『居酒屋ふじ』(2015年単行本刊)について伺います。執筆に至った経緯を聞かせて下さい。

栗山 僕が30過ぎくらいからずっと通い続けている居酒屋があるんです。それが「ふじ」。6、7年前のある晩、酔っ払い同士がね、店主の「おやじ」を主人公にした映画を創ろうよって話で盛り上がって。でも酒の上での冗談半分のノリですよ、あくまでも。
── 小説を読むと「おやじ」の半生が波乱万丈で、映画にしたくなるのもうなずけます。
栗山 でしょ。それで映画には脚本が必要だけど、誰が書くのって。まあ、付き合いも長いし、一番「おやじ」のこと知ってるんじゃないかってことで僕が書くことになったんです。とはいえ、僕は脚本なんか書いたことないし、書き方もわからない。でも、そのときは、一度「おやじ」の話をちゃんと聞いておきたいという気持ちの方が勝っていたんだと思います。それで5回くらいかな、レコーダー持参で「おやじ」のマンションの部屋へ行って話を聞かせてもらったんです。「俺のことならアイツに聞け」っていわれて目黒駅前の焼肉屋の店主にも取材したな……。テープ起こししたものを、年代とかテーマごとに分けて、それを短篇エッセイのようなものにまとめていったんです、「おやじのバカ話集その一」みたいな。それがある程度できたところで、同じ「ふじ」の常連なんだけど、ノリさん(タレント・木梨憲武さん)に読んでもらったんです。そうしたら「おもしろいじゃん」って言ってくれて。そのときですかね、小説にしようと思ったのは。
── ここに書かれている「おやじ」のエピソードは、にわかには信じられないような内容ですが、どの程度事実だったんでしょうか。
栗山 それは僕にもわかりません。ただ僕が創作したエピソードというのはひとつもありません。すべて「おやじ」が語って聞かせてくれたことです。ヒロポン中毒になった話も、偽DDTを売って警察に追われたことも、店名の由来となった娘のふじ子さんのことも、陰毛占いの話も(笑)。ぜんぶ「おやじ」が話してくれたことです。「おやじ」自身が盛って話した可能性は大いにありますけど(笑)。
── 作中で「おやじ」は客に自身の半生を赤裸々に語って聞かせますが……。
栗山 実際の「おやじ」もあのまんまでした。っていうか、基本、自分の話しかしなかった。たとえば客のひとりが弱音を吐いたとするでしょ。そうすると「そんなのは、おとうさん(自分のこと)なんかねえ」って自分の話を始めちゃう。で、さんざっぱら自分がどんなヒドい人生を歩んできたかってことを話したあとに「だから大丈夫だ」って(笑)。でもね、それがいいんですよ。どこかで聞いたふうな励ましの言葉とか絶対言わなかったから。
小説書いて改めて思うのは「おやじ」ってナマ傷の絶えない人だったなってことです。自分が傷つかないように小器用に振る舞うこともできたはずなのに、それをしなかった。そこがまたカッコいいんですけどね。おまけに傷ついてもじっと快復を待つってことができないタイプで、傷が治りかけたころに痛痒くなってかさぶたを剥がしちゃうみたいなところがあって……。
── 「おやじ」のエピソードでとくに印象深い登場人物がいます。娘の「ふじ子」と、奥さんの「光子」です。
栗山 「おやじ」のインタビューで、競輪の次に多かった話題がふじ子さんのこと。愛情表現が下手な父と娘なんですね。どちらからでもいいからひと言素直な気持ちを伝えればいいのにと思うんですけど、結局その機会は永遠に得られなくなってしまうんです。僕は残念ながらふじ子さんにお会いすることがなかったので、父と娘が登場するシーンは僕の想像で書かせてもらいました。「おやじ」だったらこう言うだろうし、ふじ子さんだったらこう返しただろうなって。この焦れったくて、温かくて、微妙な父娘関係は、とりわけていねいに書きたいと思ったし、書いていて一番楽しかった。
光子さんは本当に芯の強い人。だって「おやじ」の過去も全部知った上で一緒に歩んでいこうと決心した人ですから。プルーフ版(発売前の見本書籍)ができたときにおかあさん(光子さん)に持って行ったんですよ。そうしたら本を胸に抱きしめて泣いてくれました。後日感想を聞いたら「いやぁ、小説の『光子』は本当にいいオンナ。これ読んで店に来た人は実物みてがっかりしちゃうんじゃない?」なんて笑ってました(笑)。
── 本作は主人公の「西尾栄一」が生きる現代の物語の間に、昭和、平成と生きた「おやじ」のエピソードを入れ込んだ二重構造で展開していきます。これには何か意図があったのでしょうか。「おやじ」の半生単独でも充分面白いと思ったのですが。

栗山 「おやじ」の伝記を書く気はさらさらなかったんです。
そもそも人間は愛されるために生まれてきた、って僕は思っているんですよ。その思いを強くしてくれたのが「おやじ」の存在。だってあんなにぐうたらでロクでなしのダメ人間なのに、みんなに愛されていたんだもの(笑)。あの「おやじ」と接したら自分が抱えている悩みなんか小せぇ、小せぇって思えてくる。これは僕、ひいては「西尾」の視点です。
僕がこの物語で伝えたかったのは、「おやじ」の武勇伝ではなく、こんな「おやじ」がいるような居酒屋に出会えるか出会えないかで人生大違いだぞ、ということ。その意味でも「西尾」の物語は必須だったんです。
── 本作は売れない役者である「西尾」の成長譚でもあります。でも劇的に変わっていくというサクセス・ストーリーではないですよね。
栗山 そう、そう。連ドラの主役を張ったり、ハリウッドに進出したりするような役者になればドラマチックなんだろうけど、そんなふうにはならない。少し舞台の仕事が増えるくらいで、社会的な立ち位置っていうのはほとんど変わらない。でもね、内的には〝劇的〟に変わったんです。最初「西尾」は役者になりたいと、熱量もそれほどなく漠然と思っていた。ようやく舞い込んだ初主演の舞台の自己評価も60点止まり。それでショゲて「ふじ」に顔を出すと「おやじ」に〝俺なんか0点以下だ〟ってドヤしつけられて自分を見つめ直す。そんなことを繰り返しながら、最後に「西尾」は〝自分も90点取れるんじゃないか〟って思えるようになる。これは大きな成長です。そしてその成長は「ふじ」に通わなきゃ実現できなかった。
だから「ふじ」って教室なんです。「おやじ」は、ぜんぜん先生らしくないけど(笑)、そこの教師。いろんな客が来て、生徒としていろんなことを学んでいくんです。同じことをまた言いますけど、僕は「おやじ」の物語を書きたかったんじゃない。こんな「おやじ」がいた「居酒屋ふじ」を書きたかったんです。
── なるほど。さて、この物語に文庫本で初めて触れる読者もいると思います。そんな人にメッセージはありますか。
栗山 そうですね……。もし共感できるところがあったなら、ぜひあなたの身近なところに、あなたの〝居酒屋ふじ〟を見つけて下さい。それは必ずあります。そしてその店はあなたの人生に潤いと輝きを与えてくれることでしょう(笑)。
── 『居酒屋ふじ』の「おやじ」もそうですが、2作目の『国士舘物語』(2016年刊)には主人公「江口孝介」の父親やクラス担任の「茶村先生」、アパートの大家さん、と敗戦を経験して戦後をたくましく生き抜いてきた方が登場します。この戦中派世代の描き方には、栗山さんが抱く彼らへの敬意や共感といったものを感じるのですが。
栗山 父親が湾生(日本統治時代の台湾で生まれた日本人)なんですよ。父の父、つまり僕の祖父は将校で、台北高等学校(現在の台湾師範大学の前身)の教授をしていたそうです。父は昭和2(1927)年に台湾で生まれて、昭和13(1938)年に祖父が亡くなって日本に引き揚げてきたんです。台湾ではお手伝いさんが2人いて随分と優雅な暮らしぶりだったみたいです。そう話す父はといえば岐阜の田舎町で地方公務員をやってるんですから、息子としてはどうせ眉つばだろって半分信じてなかった(笑)。それでも父は「台湾はいいところだから一度連れてってやる」って言ってたんだけど、早くに亡くなってしまって。
自分が50になったとき、このままじゃ父が僕に見せたかった台湾に行かずじまいになりそうな気がして、兄と2人で行くことにしたんです。祖父が勤めていた台湾師範大学にも足を運んだんですけど、購買部をのぞいたら、その書棚に創立七十周年の記念本が販売されていたんです。何気なく手にとってページを開いたら、歴代の先生のリストが掲載されている。「これは!」と思ってリストを目で追っていったら、なんとあったんです、祖父の名が。「栗山又治郎」って。そうしたら兄貴が僕から本をひったくって「ビッグサプライズ! ディス・イズ・マイ・グランドファーザー」って叫びながら誰かれ関係なく見せるんですよ。その小躍りしている兄貴を見てたらなんか泣けてきちゃって。そのうち学生たちがまわりに集まり出して、兄貴は「これは俺のじいさんだ」って叫び続けてるし、学生も口々に「おめでとう」「おめでとう」って。なんか小っちゃないいシーンになっちゃいました(笑)。
戦争を生き抜いた人が身近にいたというのは、たぶん僕らが最後の世代になるんじゃないでしょうか。だから彼らの苦労もなんとなくわかる気がするし、そうした思いが文章に表れるのかもしれないですね。