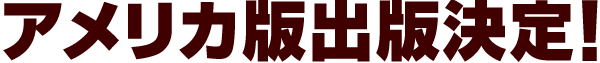アーサー・コナン・ドイルは、自みずからの本分は歴史小説にあると考え、シャーロック・ホームズのシリーズを書き続けることに嫌気が差していた。もうやめたいと母親に相談したけれども「とんでもない」と引き止められた。そこでコナン・ドイルは、決定的な終わりを迎える物語を書いた。ホームズを悪の帝王モリアーティ教授とともに、ライヘンバッハの滝つぼへ突き落とし、殺してしまったのだ。〈ストランド・マガジン〉1893年12月号掲載の「最後の事件」である。
それ以来、読者と編集はホームズの新作を求め続けた。コナン・ドイルはそれを拒否していたが、8年後の1901年、『バスカヴィル家の犬』の主役としてホームズを復活させる。但しこの際は、「最後の事件」以前の事件としてだった。
ホームズが死亡していたと思われ不在だった時期(ホームズ研究家=シャーロッキアンは「大失踪期間」と呼ぶ)に何をしていたのかについて、「チベットなど東洋へ行っていた」と説明されるものの、詳述されることはない。
その謎に秘められた期間、ホームズは秘かに日本に渡っており、伊藤博文とともに難事件を解決していた。それも、歴史に残る重大な出来事に隠された真実を。
──それが本書『シャーロック・ホームズ対伊藤博文』なのである。
ホームズが来日していたなどと、奇想天外に思えるかもしれないが、実はそうでもない。ホームズはライヘンバッハでの対決の際、「バリツ」という日本の格闘技を用いたおかげで助かったのだ(もちろん本作にも登場する)。日本の文化となにがしかのかかわりがあったホームズが、アジアへ行ったのなら日本に行っていた可能性もあるというものだ。実際、そういう説に前例もある(詳しくは後述)。
日本に来ていたからには、当時のあの人物やこの人物に会っていたかもしれない、と考えるのが当然だ。ここで作者が選んだのは、他ならぬ「伊藤博文」だった。
伊藤博文(1841~1909)は、討幕運動に参加したが、明治維新後は憲法制定の中心人物となり、初代首相にまで上り詰めた人物。シャーロック・ホームズの相手をするに、不足はない。
日本人は『モスラ対ゴジラ』や『ガメラ対ギャオス』のような〝対決〟モノが大好きだ。但し本作では、ホームズと伊藤博文は反発する側面もあるけれども、実質的には協力して事件の捜査に当たる。これも『マジンガーZ対デビルマン』のように、〝対決〟タイトルでありながら実際には〝共闘〟という、日本ではお馴染みのパターンなのである。シャーロック・ホームズは世界的にヒットした〝バディもの〟の元祖と言えるが、その相棒たるワトソン博士の日本における代理となるのが、伊藤博文だったわけだ。
本作では、歴史上の出来事とシャーロック・ホームズの年代記を巧みに組み合わせている。博文は1863年から64年にかけて、実際に仲間とともに渡英している。だからこの際に、博文とホームズの(最初の)出会いがあっても不思議ではないのだ。その時博文は22歳、ホームズは10歳。博文が12歳、年上である。
そしてホームズの大失踪期間は1891年からとされており、博文は50歳頃、ホームズは37歳。
さて、その1891年(=明治24年)、我が国で重大な出来事が発生する──来日したロシアのニコライ皇太子が巡査・津田三蔵に切りつけられるという、いわゆる「大津事件」である。ホームズが調査に乗り出すのが、この一件である。更には、ちょっと奇妙な盗難事件も。これが後にひとつの大きな流れに結びついていくのだ。
本作は虚実の混ぜ具合が、実に絶妙だ。山田風太郎や横田順彌の明治小説と似た味わいの、重厚でありながら第一級のエンタテインメントなのである。
正典(コナン・ドイルによる原作)に基づく要素も、バランスよく配されている。シャーロッキアンには説明の要はなかろうが、ざっとピックアップしてみよう。
ホームズが「かつて死んだと思われながら生きていた男」として回想する「ネヴィル・セントクレア」とは、「唇のねじれた男」に登場する人物だ。
ホームズが教師に投げかけたという「繁殖した牡蠣がなぜ海底を埋め尽くさないのか」なる疑問は、「瀕死の探偵」に出てくるホームズの言葉。
伊藤博文がベーカー街221Bにあるホームズの部屋を訪ねた際の室内描写も〝なかなか分かってる〟感じだが、「大きく捻じ曲げられたのち、元へ戻したように見える」火搔き棒については、「まだらの紐」を読んだことのある方ならば、どうしてそうなったか思い出してニヤリとすることだろう。帰宅するホームズとワトソンは「まだらの紐」事件から戻ったところだったのだ。
シャーロックの兄マイクロフト・ホームズが「ギリシャ語通訳を救った」というのは、そのままずばり「ギリシャ語通訳」事件である。
「青いガーネットを盗んだ男」をどうするか、ホームズが自ら判断した、というのもずばり「青いガーネット」事件。
ホームズが「かつてテムズ川で追跡したオーロラ号」というのは、『四つの署名』事件に出てくる汽艇(ランチ)の名前で、この追跡のくだりはホームズ物の中でも屈指の名シーンだ。
これ以外にも、様々な要素がうまくちりばめられている。「最後の事件」及び「空き家の冒険」については、言うまでもない。普段からホームズ・パスティーシュを書いているのかと思えるぐらいな見事さだ。
また、ホームズ要素もただ再話・引用するのではなく、作者なりの解釈が加わった形で消化(昇華)されているのだ。ホームズとモリアーティの対決(及びその後)しかり、シャーロックとマイクロフトの兄弟関係しかり。
「まだらの紐」事件に登場する毒蛇の生態の問題点についても(動物学者でシャーロッキアンの實吉達郎などにより指摘されているのだが)きちんと着目し、解決を与えている。
しかし本作は何より小説として面白いため、正典由来のポイントなどを(解説を書くため)チェックしつつ読まねばならないのに、そんなことをすっかり忘れて一気に読み通してしまった。
本作は、いわゆるシャーロック・ホームズ「パスティーシュ」である。パスティーシュとは、原作と同じ世界観やキャラクター造形を踏まえ、他作家が生み出した新たな物語であり「本歌取り」や「トリビュート」である(茶化したりしたものは「パロディ」とされるが、その境界線は微妙)
我が国にホームズのパスティーシュ/パロディが導入されたのは、大正元年(1912年)、安成貞雄「春日燈籠」である。これはルブラン『ルパン対ホームズ』の後半に当たる中篇「ユダヤのランプ」の翻案だった。
日本人が初めて書いたのが、大正13年(1924年)の水島爾保布(におう)「アリッシュマン伯と三探偵」。しかしその後も翻訳が主流であり、日本人のものはほとんどが短篇か中篇だった。
その大転換となるのが、1983年の加納一朗『ホック氏の異郷の冒険』である。これは大失踪期間にホームズが偽名で来日していた、という長篇で、日本推理作家協会賞を受賞した。翌年(1984)には島田荘司『漱石と倫敦ミイラ殺人事件』が発表される。こちらはホームズがロンドンで夏目漱石と出会う、というもの。この2作により、日本人作家による、ホームズ・パスティーシュ長篇が「解禁」されたのだ。
漱石はすごくいいタイミングで渡英しているため、ホームズ・パスティーシュに使われやすい。島田荘司以前にも、山田風太郎が短篇で書いている。本当は、漱石が出てくると明かしてしまうとある意味ネタバレなのだが、ここではご容赦頂こう。「黄色い下宿人」(1953年)である。逆に島田荘司以後には、柳広司『吾輩はシャーロック・ホームズである』(2005年)がある。
キャラクターを犬化したアニメ『名探偵ホームズ』の第19話は、「漱石・ロンドン凧合戦!」(1985年)というエピソードだ。
本書『シャーロック・ホームズ対伊藤博文』は、基本的には『ホック氏の異郷の冒険』と同じ〝ホームズ訪日〟パターンであるが、過去パートでは『漱石と倫敦ミイラ殺人事件』と同じ〝ロンドンで日本人に遭遇〟パターンも混ざり込んでおり、折衷型なのである。
ホームズが日本に来るパスティーシュは加納一朗以前からあった。その最大の例が山本周五郎『シャーロック・ホームズ』(1935年)である。これは複数の正典を組み合わせて新たな物語を作り上げてしまったものだが、事件は日本で発生し、ホームズが来日するのだ。但しこれは大失踪期間には設定されていない。それどころかこの物語の中でホームズは軽井沢の滝に落下し、死亡した(と思われる)のだ。
海外のパスティーシュについても少しだけ。大失踪期間のホームズを描いたものとしては、ジャムヤン・ノルブ『シャーロック・ホームズの失われた冒険』やテッド・リカーディ『シャーロック・ホームズ 東洋の冒険』がある。
ヴァスデーヴ・ムルティ『ホームズ、ニッポンへ行く』も同様だが、インド人作家が書いたためか非常にユニークで、明治天皇が浴衣姿で秘密会議に出てしまったりする。
近年ではミッチ・カリン『ミスター・ホームズ 名探偵最後の事件』の中でも、ホームズは日本を訪れている。但しこれは老境のホームズの物語なので、太平洋戦争終戦直後の日本だが。後に『Mr.ホームズ 名探偵最後の事件』として映画化もされ、重要な日本人役を真田広之が演じた。
『シャーロック・ホームズ対伊藤博文』は、細部までシャーロッキアン的な視点で描かれている。ここまで書ける作者は、立派なホームズ専門家だと言っても過言ではない。同じテーマでは難しいかもしれないが、新たなアプローチでならばまた傑作ホームズ・パスティーシュ物語を書けるはずだ。
これからも大いに期待したい。
閉じる