
大災厄に見舞われた後、外来語も自動車もインターネットも無くなった鎖国状態の日本で、死を奪われた世代の老人義郎には、体が弱く美しい曾孫、無名をめぐる心配事が尽きない。やがて少年となった無名は「献灯使」として海外へ旅立つ運命に……。
収録作
「献灯使」 「韋駄天どこまでも」 「不死の島」 「彼岸」 「動物たちのバベル」
留学中に故郷の島国が消滅してしまった女性Hirukoは、ヨーロッパ大陸で生き抜くため、独自の言語〈パンスカ〉をつくり出した。Hirukoはテレビ番組に出演したことがきっかけで、言語学を研究する青年クヌートと出会う。彼女はクヌートと共に、この世界のどこかにいるはずの、自分と同じ母語を話す者を捜す旅に出る――。
誰もが移民になりえる時代に、言語を手がかりに人と出会い、言葉のきらめきを発見していく彼女たちの越境譚。
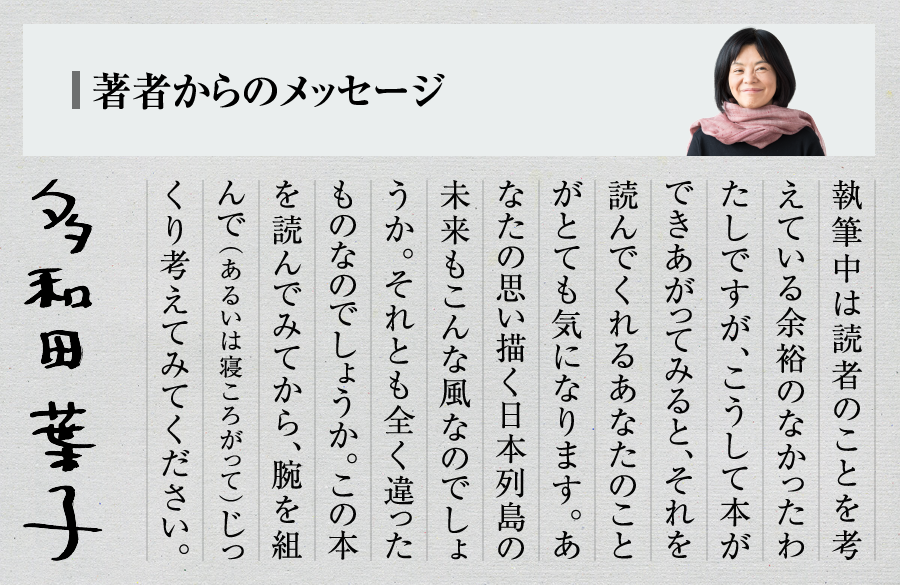
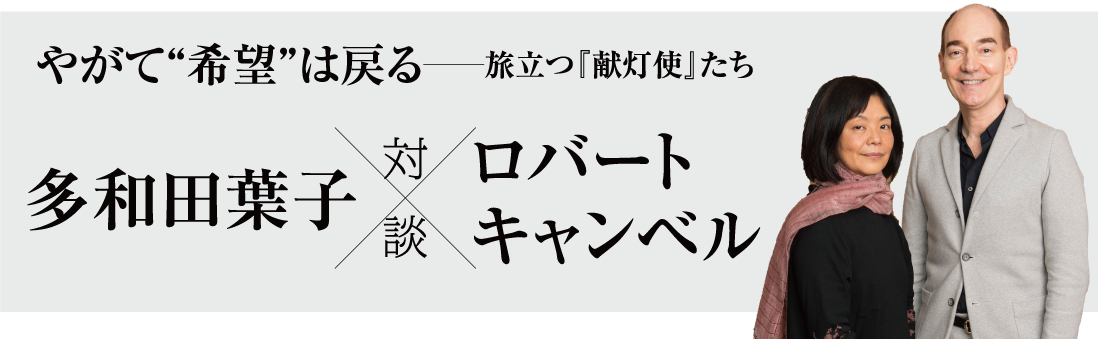
これは「未来」ではない
多和田 皆様、どうもきょうは遠いところ、また近いところ、ようこそおいでいただきました。
10月30日に出たばかりの、まだインクが手につきそうな『献灯使』ですけれども、この本は、無名という男の子と、その曾おじいさんに当たる義郎が、主な登場人物になっています。無名は身体をあまり自由に動かすことができないのですが元気で、義郎もたいへん歳をとっていますが元気です。義郎だけでなく多くの老人が、百歳を過ぎてもまだ死ぬことができません。身体の弱い子供と、その面倒をみる老人、そういう二つの世代の物語です。
この小説では、日本は鎖国をしています。外来語を使ってはいけないという不思議な規則があったり、ほかにも秘密保護法のような法律があるのではないか、そんなふうににおわせる設定になっています。
長くなりましたが、初めまして、キャンベルさん。きょうはよろしくお願いします。
キャンベル こんばんは。こちらこそ、よろしくお願いします。多和田さんとは、ほんの1時間前に初めてお目にかかったばかりです。著者を前に作品について話すのは緊張しますが、初めてお目にかかるのがこういう場だったというのは、私の記憶に鮮明に残るのではないかと期待もしています。
表題作の「献灯使」は、「群像」8月号に掲載されたとき、一気に読みました。気になる部分に赤ペンで書き込みをしながら繰り返し読んでいたので、よれよれになってしまった(笑)。私は多和田さんの作品が好きで、小説もエッセイもいくつも拝読していますが、東京一円が舞台の長篇を読んだのは、今回が初めてではないかと思います。ですから、普段はドイツにいらっしゃる多和田さんと、こんなふうに東京でお会いして対談ができることは非常に嬉しいです。
多和田 たしかに、最近の作品はそうですね。『雪の練習生』や『雲をつかむ話』もドイツなどが舞台でした。でも、『犬婿入り』というのを昔書きまして、それはわたしの育った国立が舞台になっています。
キャンベル 国立は東京ではなく東京「都」です(笑)。
多和田 そうでしたか(笑)。
キャンベル 義郎と無名も「東京の西域」にある仮設住宅に住んでいますね。東京という都市空間を表現する方法として、東京を拠点として長いこと暮らしている人であれば、東京特有の固有性や求心力を、ぐっと押し出して描くと思います。もしくは、サイエンスフィクションのように、普通に読んでいてはなかなか気づかないレベルまでデフォルメをするかもしれない。しかし『献灯使』は、どちらの方法もとっていないんですね。新宿や成田空港といった固有名詞は出て来るものの、私たちが識別できるような風景は全く描かれない。具体的でありながら、不気味なほどに特定しづらい。それが、この小説の基本的な情景です。
また、無名をはじめとする子供たちは、どういう状況で歩行にも難儀するような身体になってしまったのか。百歳を超える老人が健康で、死ぬこともできないのは何故なのか。日本はどのような歴史的背景でもって鎖国に至ったのか。外来語を大っぴらに使うのはどんな法に触れて、どう処罰されるのか。多和田さんは先ほど「におわせる」という言い方をされましたが、まさにおっしゃるとおりで、不可思議な設定の根本にあるものは最後まで明らかにされません。無名と義郎が暮らす東京西域の様子がたいへん精緻に構築されていることと比べると、日本の現状やそれに至る経緯は、まるで霧に包まれたように不可解です。
私は最初、土が汚染されているんじゃないだろうかと考え、この小説は三・一一と原発事故を経た日本の未来図ではないかと思ったんですね。もしくは、第三次世界大戦のような何か大きな戦争を経験した世界なのか、とか。けれど作中に、震災や原発、戦争という単語は、全く姿を現しません。すべて私たちの頭の十センチぐらい上にぶら下げたままにして、多和田さんは筆を置いたんだなという印象があるんですが、そこにはどんな思いがあったのでしょうか。
多和田 そうですね。私としてはもちろん原発事故のことを頭から追い出すことはできません。今再稼働したらその後の日本はこうなるのではないかということは考えました。でも、原発は自然破壊の山頂みたいなもので山全体はもっと大きいし、また自然だけでなく人間も破壊されていると思います。例えば作中、町は機能しているのに人間が全くいなくなった都心の光景が出てきます。これは、いまの東京を見ていて、私が時々感じることでもあるんです。みんな無理して細かい規則に従って動いているんで、すべてがちゃんと機能しているように見える。でも、そのせいで、これだけたくさん人間が住んでいるのに誰もいないような感触もある。ベルリンだったら、家のない人とか、通りでたむろする無職の若者とか、電車のストライキとか、機能しない部分がはっきり目に見えるので、かえって安心です。人間は機能するために存在するわけじゃないと思うので。でも、東京は負の部分が隠れている。だから、信号も動いているし、車も走っているし、お店もちゃんと営業しているけれど、なんだか無人のような気がすることがあって、それを見ているので、人のいなくなった新宿を想像するのはそれほど難しくなかったんです。
原発事故は一度大きな事故が起こってしまった、というよりは、何十年もの間、積み重ねてきたいろいろな間違いが一気に噴火した感じでした。今現在はまず原発を再稼働させないことが何より大切ですが、それ以外にも困ったことがいろいろあると思います。金儲けのためなら人が死んでも仕方ないという考え方そのものをどうにかしないと、多分ひどいことになってしまう。
放射能については、子供のほうが細胞分裂が速いので、被曝した場合に老人と比べて大変な病気にかかる危険が大きいと言われてますね。無名も含めて子供たちは自分で歩くことさえできないんですが、義郎たち老人は、これまでの体力を保つことに成功している、というか、そうするしかない状況にあります。それどころか年寄りは放射能に当たると死ななくなる、という設定になっています。もっと正確に言えば、本当にそうなのかは誰にもまだ最終的にはわからないという設定ですけれど。「日本がこんな状態では死ぬに死ねない」と言っている方がいて、それを聞いたとき、「死ねない」という発想は深刻だけれど面白いなと思ったんです。
実際、日本は寿命がどんどん延びてきましたよね。その一方、若者の数は減少の一途で、体力も落ちてきている。ですから元気な年寄りが日本社会を支えていかざるを得ない。そういう社会構造はすでにあるわけで、そういう意味でも『献灯使』は未来小説じゃないんです。
キャンベル 未来小説じゃないというところに、私はとても惹かれています。機能としての人間という言葉がありましたが、視点人物の一人である義郎は、それとは真逆のとても泥臭い男ですね。彼は曾孫の無名に対して、守ってやりたい、いろいろな経験をさせてやりたいと強く思っており、無名の両親でも祖父母でもなく、さらに上の世代の自分が曾孫の面倒を見ることを是認しています。けれど、物語の終盤、無名を学校に送り届けた帰り道で、突然たいへんな怒りを抱くんですね。「孫のことは娘に任せて、曾孫のことは孫に任せて、あの空の向こうに飛んで行ってしまえたらどんなにいいだろう。」
この怒りは無名や家族に向けられたものではなく、彼らが生きる社会、状況に向けられています。「野原でピクニックしたいって、曾孫はいつも言っていたんだよ。そんなささやかな夢さえ叶えてやれないのは、誰のせいだ、何のせいだ、汚染されているんだよ、野の草は。どうするつもりなんだ。」
曖昧模糊とした不穏さ漂う世界で、唯一この義郎という老人が真正直に生きている。曾孫への情熱や、社会への怒りといった生々しさが、逆に小説の中で光っているように感じます。
義郎は主要登場人物の中で一番の年長者ですから、時間の流れに意識的です。木の年輪を思い浮かべて、死ねない自分の身体には、どんなふうに時間が保存されているのか、と考える。死ねないという苦しみは、作中ところどころで描かれています。例えば、近所の絵はがき屋で買い物をするシーン。「絵はがきならば、書き始める前から終止符が思い浮かぶほど書く場所が狭い。終わりが見えていると、かえって安心する。医学の最終目的は決して死なない永遠の身体をつくることだと子供の頃は思い込んでいたが、死ねないことの苦痛については考えてみたことがなかった」。これを読んで、私は正岡子規の『病牀六尺』を思い出したんです。新聞連載をもう百回分書いたけれど、原稿を送るための封筒がまだ200枚も残っていることに重圧を感じる、と子規はいうんですね。死ぬことのできる子規ですらうんざりするのに、義郎に至っては不死なわけです。「『切手千枚』を特別価格で売っていることもあるが義郎はそれを見ると、千枚も絵はがきを書いてもまだ死ねないことを思い知らされるようで買う気になれない」というのにも納得です。
多和田 これは昔からそうですが、いつ死ぬかは誰にもわからないんですね。最近はそれに加えて、できるだけ若さを保つことが人生の目的みたいな考え方さえある。ですから私たちは、どういうふうに年をとっていけばいいのか、オリエンテーションに苦心しながら、日々を過ごしているわけです。現代医学も年のとり方は教えてくれません。この小説に出てくるような死ねない老人は、私たち以上に人生の区切りに苦労することになると思うんです。
作家は、作品を書き終えるごとに、ひとつの時間が過ぎたんだなという実感があって、これが人生の区切り目になることもあります。でも、作家でなくとも、紙に書くという行為は、区切りをつけやすいと思うんです。手紙やはがきは1枚、2枚と数えられますし。切手も同じで、使えば使うだけ減っていく。それから『献灯使』の世界では、インターネットがなくなっているので、一度死滅した新聞文化も復活しています。
キャンベル インターネットがなくなった日を祝う「御婦裸淫の日」がありますね。漢字がとても面白い(笑)。
多和田 そうです(笑)。インターネットがなくなって、紙の文化に戻っています。
キャンベル 子供の健康状態に関するデータも、すべて手書きなんですよね。
多和田 手書きのほうが、商業利用、あるいは政府に盗用されたり改竄されたりしづらい、絶対安全だという方向に、セキュリティーが発展したんです。だから医師たちは、手書きのカルテを犬小屋の奥や大型煮込み鍋の中に隠している。
笑いながら真剣に考える
キャンベル 今年お書きになったエッセイ、「カラダだからコトの葉っぱ吸って」に「気をつけろホルモン」という言葉を書いてらっしゃいましたね。「犯罪の多い場所に行くと、身体が信号を受け取って『気をつけろホルモン』が出る。このホルモンが出続けていたらすぐに疲れて病気になってしまうかもしれないが、短い期間なら創作活動にとってはとても有益である。このホルモンが出ると、5つ以上の感覚が最大限に活性化される」。私は犯人との関係を描いた長篇『雲をつかむ話』が大好きなのですが、多和田さんの小説には、危険を感じることで生きる手応えや実感を得る、というようなところがあるように思います。
『献灯使』では、身近どころか主人公の周囲全てが危険な状態に置かれていますが、それは具体的には描かれない。例えば「一等地も含めて東京23区全体が、『長く住んでいると複合的な危険にさらされる地区』に指定され、土地も家もお金に換算できるような種類の価値を失った」とか、「どの国も大変な問題を抱えているんで、一つの問題が世界中に広がらないように、それぞれの国がそれぞれの問題を自分の内部で解決する」ために鎖国をするとか、これまでの、危険の気配を背中で感じるような雰囲気とは違い、危険さが旋回しているような印象を受けました。
多和田 『雲をつかむ話』は、犯罪者と犯罪者でない人たちは本当にそんなに違うのかな、という疑問から生まれた物語です。ですから、個人が法を犯してしまう可能性について書いています。一方『献灯使』は、それ自体が犯罪的である法律がどんどんできていってしまう社会を描いているとも言えます。
キャンベル しかも、法を作っている統治機構が見えないんですよね。
多和田 私は、日本にもし独裁制が来るとしたらーー来るかもしれないという不安があるんですけれどもーー政府という存在がはっきりあって、それを批判した人が牢屋に入れられるという、わかりやすい形の独裁制じゃないと思うんです。そういうものなら、世界各地に最近まであったし、今もある。そうじゃなくて、正体不明のじめじめした暗い恐怖が広がって、「怖いからやらないでおこう」という自主規制のかたちで、人間としてやらなければならないことを誰もしなくなるような恐い時代がくるかもしれないと思うんです。
日本には一応民主主義があって、選挙も規則どおり合法的に行われていて、そこに不正は少ししかないと思うのですが、何故かみんな選びたくない人を選んでしまっているようで不気味です。そういう不気味な独裁制の出だしの様子を、小説という網でとらえることができるかもしれないと思いました。
キャンベル 言葉がまず規制の対象になっていて、外来語が禁止されているんですよね。でもそれも厳しく取り締まられているわけではなくて、「使わない方がいい」という表現がされている。オーウェルの『1984年』に登場するビッグ・ブラザーのような人類を監視する目が痕跡もなくなるほどかき消された結果、自粛をするという方法で統治機構が自動運転している、そんな印象を持ちました。
それにしても、言葉が規制されているからこそ生まれた、漢字でできた外来語はどれも傑作でした。「御婦裸淫の日」もですが、ジョギングを意味する「駆け落ち」や、パンの種類の「刃の叔母」「ぶれ麵」にも「ふふっ」と笑ってしまいました。多和田さんの作品は、ちょっとした言葉遊びかなと油断していると、それがいつの間にかさらに展開して、小説の重要な部分を照らしてくれることがありますね。
多和田 私はものを考える時に、言葉に手伝ってもらうことがあるんです。それは、言葉は私よりずっと長く生きているせいか、私とは比べものにならないくらい知恵があって、私にはとても思いつかないようなアイデアを与えてくれるから。それに、今回の作品のような深刻な問題を扱う時には、どのような言葉で語っていくかによって、思考が硬直化して先へいけなくなる危険もあるし、逆にほぐれて明るく先へ続くこともあるんです。
笑いながら真剣に考えるという、二つの感情を同時に活性化するような能力を、自分でも育てていきたいと思っているんです。この笑いは決して人間を笑うようなものではないのですが、人間の愚行を笑う覚悟はあります。そして、私にとって何よりも楽しい仲間は、言葉や漢字なんです。そこで言葉遊びが出てくるんですね。
血のつながりを超えて
キャンベル 無名は着替えるだけでもひと苦労なのですが、本人はそれを楽しんでやっています。寝巻きをどちらの足から脱ごうか考えているうちに、ふと蛸のことを思い出して、自分の足も本当は8本あるんじゃないか、それが4本ずつ束ねられて2本に見えるだけじゃないのか、なんて想像して遊んでいる。
義郎は、二本足歩行に難儀する無名を、身体の機能が退化しているととても心配します。けれど同時に、もしかしたら将来、人類は蛸のようにはって歩くようになるのかもしれないと空想もする。二足歩行は人類にとって最上ではないのかもしれない、と考えるんですね。
多和田 この蛸化というのは、以前、とある舞踏家から聞いた話から思いついたんです。かつて日本にバレエが入ってきたときに、すばやく動き、高く跳ぶことのできる身体が進化した美しい身体だ、我々もそういう方向に向かわなくてはいけない、という考え方が出てきた。それもひとつの意見かもしれないけれど、西洋バレエとは全く異なる身体の動かし方も踊りの中で探っていくべきだとその人は言うんですね。それが日本的だからということではなくて、高く跳びはねるのではなく重心が下にあってもいいのだし、ゆっくりだるそうに動くのも素敵だし、くねくねと地を這うのも面白いじゃないかということです。
これから人類の身体は確実に変化していくと思いますが、それに対する受け皿がほんの少ししかなくて、とにかく速いのと強いのが偉いという狭い考え方にしがみついていたのでは、これから起こるいろいろな変化に対応していけないと思うんです。小説を書くことで、身体の可能性を探ってみたいですね。
キャンベル この小説で、ある意味衝動的に共感ができるのは、義郎が無名に抱いている、幼き者への愛おしさだと思います。
あまりにも突飛な発想なので笑われるかもしれませんが、70年代の井上陽水に「海へ来なさい」という歌があるんですね。ちょっと紹介させてください。歌詞を読むだけで、歌いませんからご安心を(笑)。
「太陽に敗けない肌を持ちなさい 潮風にとけあう髪を持ちなさい どこまでも泳げる力と いつまでも唄える心と 魚に触れる様なしなやかな指を持ちなさい 海へ来なさい 海へ来なさい そして心から幸福になりなさい」。2番は、「風上へ向える足を持ちなさい 貝がらと話せる耳を持ちなさい 暗闇をさえぎるまぶたと 星屑を数える瞳と 涙をぬぐえる様な しなやかな指を持ちなさい」。
すべて「~しなさい」という命令形なのですが、とてもやわらかい。私はこの歌は、海に来られないような子、来られたとしても魚と触れ合えないような子、そういう身体の弱い子供に向けられたんじゃないかと思っていたんですが、今回『献灯使』を読んで、初めてここで歌われている光景が私の中で固まったような感覚があります。しつけたり、教え込んだりするんじゃない。大人が子供に抱く、愛おしいという感情が表わされているんじゃないかと思ったんです。多和田さんは、いま日本の親子関係において、こういう無条件な愛おしみ合いみたいなものが薄れているように感じますか?
多和田 親子に限る必要はないと思います。無名と義郎は一応曾孫と曾おじいさんという関係ですが、血がつながっているかどうかは分からない。無名のお父さんの飛藻は無責任な男でどこかへ行ったきりですし、もしかしたら無名は、飛藻の奥さんと違う男性との間にできた子供かもしれない。だから必ずしも、家族だからとか、血縁関係にあるからとか、そういうことではなくて、これからの世代に対する思いみたいなものが義郎の中にあるんですね。
これは決して生まれた時から備わっていた感情ではなくて、原発事故のような大きな問題に直面したために生まれてきた、あるいは活性化されたのかもしれません。環境問題を真剣に考えたら、どうしても自分の死後も続く生命のことを考えないわけにはいきません。自分の子供のことだけでなく、もっともっと先の、赤の他人にあたる子供たちのことも、動物や植物たちのことまで心配になると思うんです。義郎が無名に感じる愛おしさは、家族や国家の枠組みを超えたものなんじゃないかと思います。だからやっぱり鎖国のままでは困るんです。
考えると明るくなる
キャンベル 最後に『献灯使』というタイトルについてうかがいたいです。もとになっているのはもちろん、唐に派遣された「遣唐使」で、これは小説家である義郎がかつて取り組んだ最初で最後の歴史小説のタイトルでもあります。外国を示す「唐」をなくそうと、「献灯使」という漢字の組み合わせになったこの言葉は、日本のためにーー密航ですがーー海外に派遣される子供たちを意味します。十五歳になった無名は、この使命を帯び日本を出ることになります。外に出ていくことが、非常に重要な意味を持っている。
多和田 まさにおっしゃるとおり、『献灯使』という題名には、外に出て、大陸に学ばないとだめなんじゃないか、という思いが込められています。無名は、身体は決して丈夫ではありませんが、「頭の回転が速くても、それを自分のためだけに使おうとする子は失格」、「他の子の痛みを自分の肌に感じることのできる子でも、すぐに感傷的になる子は失格」というような献灯使になるための条件をクリアできる子で、彼がいつか日本を出て、海の向こうに渡って何かを学び、交流が始まり、鎖国が終わるというのが、この小説のひとつの希望になっているんです。
キャンベル 日本から出る、だけでなく、東京から出る、というのも重要なポイントですよね。無名と義郎が暮らしている「東京の西域」は自給自足がほぼ不可能で、沖縄のような汚染されていない土地から豊かな農産物を輸入している。義郎の娘で、行動力があって決断の速い天南は、早々に夫婦で沖縄に移住しています。
食料を輸出できる沖縄は強気で、言語の輸出で経済を潤した南アフリカとインドの真似をして沖縄の言語を売り出そうか、などと考えた日本政府に、そんなことをしたら本州に二度と果物を送らないよ、と脅す。これはとても面白いです。
多和田 おっしゃるとおり、『献灯使』には、東京が他の県より重要だという考え方は全くありません。むしろその逆ですね。特に23区は住んでいる人もいなくて、西域だけが機能している。
キャンベル 多和田さんが育った国立から西ですね(笑)。
多和田 国立から奥多摩にかけてでしょうか。でも、それも東京への愛着から、あまり遠くに離れられないから仕方なく住んでいるだけで、本当はもっと遠くに行った方がいいんです。先ほど指摘していただいた沖縄なんかは実際、農業のおかげで非常に栄えていて、自分が正しいと思う政治を行うことのできる自治区みたいになっています。
それから、お金がものを言わない社会になっているんですね。食べることが一番大切になってくるから、たとえば沖縄などは、日本では沖縄でしかできないものがたくさんとれるので、発言権が強い。東京はお笑いみたいに植物の蓼を作ってみたりするのですが、全然だめで産業がない。
これも私の考えた噓ではありますが、東京から離れた別の土地、たとえば沖縄などで無農薬の農業を始めている人も最近は結構いますから、そういう傾向が実際ないわけではない。やはり、いまのことを描いた小説なんです。
キャンベル 物語は、決して明るいエンディングを迎えるわけではありません。献灯使として船に乗り込まんとする無名は、もうすぐ自発呼吸ができなくなるかもしれないとにおわされていて、とても心配です。だからといって最後の1ページを閉じたときに惨憺とした思いになるかというと、そうでもない。それは、さっきまさにおっしゃったように、真剣なお話をするのに軽やかに言葉で遊んでいらっしゃるからかもしれないし、無名と義郎の依存し合わない、けれど互いをひとつの生命として見つめ合っているような関係のおかげかもしれません。多和田さんは書いている時に、小説を読んだ後に読み手にこんなことが残るといいなとか、そういうふうに考えることはありますか?
多和田 書く側としては、書くという行為そのものに明るさを感じるんです。たとえば福島について語ったり書いたりすると、暗く重くなってしまうから避けるという人がいますが、私はそうじゃなくて、むしろ語ったり書いたりした方がいいと思う。だってそれは他人事ではないのだし、第一どんなことをしていても不安は決して自然に消えてくれるわけじゃない。だったら真正面から見つめて、言葉をフル回転させて考えたり、書いてみるんです。すると明るくなってくる。考えるという行為、そして書くという行為は、脳みその中に電気がバーッとつくような、エネルギーを生むんです。こんないい発電の方法はないですよ。自然を破壊しないで発電できる(笑)。
キャンベル 「気をつけろホルモン」もいらないんですね。なるほど。
多和田 「気をつけろホルモン」は、観察しているときに出ますね。社会現象を観察していると怖さを感じて「気をつけろホルモン」が出る。そうすると、もっとよく観察できるようになるんです。その上で、いろいろ考えながら小説を書いていると、今度は「幸福ホルモン」が出てきますね。まあ、そういうホルモンが本当に存在するのかどうかは知りませんし、「幸福」という言葉もかなり疑ってかかった方がいいのでしょうが、これは単なるものの例えです。
書き手である私が、読み手の感想を操作するつもりは全くありませんが、読む人も、私が書いているときと同じように、ただ文字を追うのではなくて、自分でいろいろ考えながら読んでくれていると思うんです。そうすると、その考える活力によって、非常に気分が明るくなるんじゃないかな。そうだといいなと思ってます。
キャンベル ありがとうございました。
質疑応答
私は、キャンベルさんがおっしゃるのとちょっとずれてしまうかもしれないんですけれども、義郎が心配してあれこれやってあげているのに対し、無名が、僕と曾おじいちゃんは、身体も立ち方も何もかも違うからなあと悟っているようなところに、逆にすごく希望を感じたんです。
曾おじいちゃんは僕にいろいろ食べさせようと必死になっているけど、僕はあんまり食べなくても平気なんだよな、ほんとによく食べるよな、あの世代は、なんて見ているのがとても面白くて。上の世代は今の手持ちの材料だけですごく心配して人類は亡びるかもしれないと思っているけれど、全く違う体を持った蛸人間の世代は、また蛸人間の価値観とかシステムの中で全く違うことに幸福を見出して、私たちが不幸と思っていることさえ、もしかしたら幸福だと思って生きていくのかもしれない、と不思議な希望を見出した感覚がありました。
多和田 どうもありがとうございます。まさにそういうところもあると思います。『献灯使』は、一人の視点から書いている小説ではなくて、視点の転換があります。無名と義郎は助け合い、しっかりつながってはいるけれども、二人のものの見方が一致しているわけではないですよね。義郎は自分の見方を無名に押しつけるのではなく、無名も自分なりの見方を伸び伸び発展させていく感じで、私も無名のもののとらえ方にむしろ共感できるところもある。そこに希望があるかもしれませんね。
キャンベル いまおっしゃった、無名の、僕はそんなに食べないからなあというシーンは、私も印象的でした。曾おじいさんの積んできた経験や、それから生み出される価値観や考えは自分には想像もつかないけれど、自分がとても大切にされていることはよくわかる。だから、曾おじいさんを困らせたりすることはしたくないなと、彼を尊重している。私はそこに、無名の健気さや、自立した精神力を見て、大人と渡り合っていく力を、すごいリアリティーを持って描いておられるなと感じました。
今回の本には、表題作の「献灯使」以外に、「不死の島」「動物たちのバベル」「韋駄天どこまでも」「彼岸」という全部で五つの作品がおさめられていますが、全て震災をモチーフにしています。一番古い作品が「不死の島」(二〇一二年発表)、その後、戯曲の「動物たちのバベル」(二〇一三年発表)、そして今年に入って「韋駄天どこまでも」「献灯使」「彼岸」と三作発表されています。このような多様な形で震災をテーマに小説を発表される意図は最初からお持ちだったのか、また今後このテーマはまだ書き続けられるのか、おうかがいしたいと思います。
多和田 「不死の島」は震災のすぐ後、ほんとに差し迫った不安に押されて書いてしまった短篇です。小説を書くにはまだちょっと早いけれども、これだけは書いておかないと我慢ができないという気持ちでした。でも、短篇としてできあがった後も、これだけでは終われないという気がしたんです。本当はもっと長いものなんだという思いが、ずっと残っていました。
その後、震災について何作も続けて書こうという意図は特になかったんです。でも、全然違うテーマを考えていても、震災抜きでは今の日本は書けない。ですから、結果として、震災をめぐる一冊をつくることができました。
「不死の島」を書いた時はまだ福島に行っていなくて、ドイツから見て思っていたことを小説にしました。一方「献灯使」は、福島に行って、そこにまだ暮らしている人たちと話をしているうちに、だんだん違った形で膨らんできたものがあってできあがりました。最初は、「不死の島」をそのまま長くするつもりだったのですが、それはあり得ないと気がついたんです。そこで、別の立ち位置から、もう一度、若者が弱っていて、年寄りが死ねない時代を書いたのが「献灯使」です。
福島に行ったとき、また書いてみたいと思うきっかけになったような出来事はあったんですか。
多和田 一つの出来事というより、見たもの、聞いた話、すべてショックでした。仮設住宅に住んでいる人たちは、一見驚くほど普通に日常生活を送っているようなのですが、話を聞いてみると、身近に無数の問題があるんだということがわかりました。もちろん仮設の問題だけではありません。食べるもの一つ一つについて、毎日三食、これは子供に食べさせても大丈夫なんだろうかと心配する人も当然います。祖母のつくった野菜を孫に食べさせるかどうかで夫婦親子の間に意見の相違が当然生まれ、喧嘩も起こります。また子供が外に遊びに行くたびにお母さんが心配して、一日に三十分以上は外では遊ばないという規則をつくったりもする。外という空間が基本的に危険な空間になってしまった人間の暮らしなんて悲しすぎますよね。それから、よく覚えているのは、子供が植え込みのお花を摘もうとすると、「お花に触ったら危ないわよ」とお母さんが注意をしていたんですが、実は、花は危ないものだという意識を持って子供が成長していくことに胸を痛めながら注意しているんですね。そういう日常生活の中に隠れたつらさや苦しさの一つ一つに驚きました。それで気がついたら「不死の島」とはまた違った「献灯使」という小説ができていました。
(2014年11月5日、オトノハカフェにて行われた『献灯使』プレスイベントを収録しました)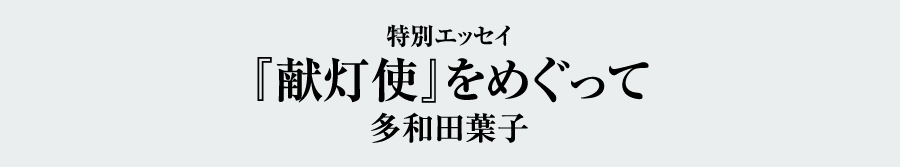
2011年3月、東日本大震災が起こった時は、ベルリンの自宅にいた。
まずラジオのニュース、そして隣の人の声、そしてインターネット、そして新聞というように情報がどんどん覆い被さってきたような気がする。友人から「休暇で北海の島に来ているのだけれど、ずっとテレビの前にすわったきり。散歩に出て新鮮な空気を吸いたいのに、恐ろしい津波の映像に縛られて動けません」というメールが来た。わたしはその津波の映像は見たくないな、と思った。数週間後に見るならいいけれど、世の中がその映像にのまれている間は見たくないなと思った。幸いテレビは持っていない。
さて、「メルトダウン」という言葉がマスコミにちらほら現れ始めると、まわりのドイツ人たちの質問の礫がいっせいに飛んできた。これは、わたしだけでなく、ドイツに住む多くの日本人が体験したことだと思う。「どうして逃げないのか」なぜ海外に逃げないのか。
わたしには、原発の近くに住む人たちが、たとえ受け入れてくれる家があるからといって、すぐにドイツに引っ越してくるとは思えなかったが、なぜそうなのか、うまく説明できなかった。海外生活の不安や苦労なんて、放射能を浴びる恐ろしさと比べれば何でもないだろう、とドイツ人に言われると、確かにそれはそうだと思ってしまう。
ところが、インターネットで日本語の書き込みをみていると、もっと違和感を覚えさせられる反応が現れ始めた。福島付近(東京もその中に入るが)から避難した家族を攻撃する書き込みだ。小さい子供がいるから京都に引っ越したという家族を罵倒するなんて、一体どういう心理なんだろう。確かに、すぐに引っ越せるだけの経済力がない人もいるかもしれない。でももし経済格差に腹を立てるなら、なぜ恐ろしく会費の高いゴルフ場でゴルフしている人への罵倒の言葉がネットに見あたらないのだろう。なぜ放射能から子供を守るというまともなお金の使い方をした人が、じめじめと暗い悪口を言われなければならないのだろう。
「自分だけ逃げるのは卑怯」というセリフが一人歩きしていた。その場に残って他の人を助けられるなら残る意味はあるが、何もできないならば、逃げられる人から逃げた方がいいのではないのか。この問題にはずいぶん悩まされた。そんな中、2011年の夏に書いたのが、「不死の島」だった。ゲイシャ・フジヤマのフジは「富士」だけれど、太平洋の隅っこで大陸に身を寄せる美しい列島が「不治」ではなく「無事」であることを願い、できれば「不死」であってほしいとさえ思いながら書いた。ニッポンを人が住めない汚染された場所にしてしまおうとしている集団が存在しているような気がしてきて、むしょうに腹がたった。この集団は、総理大臣も天皇も歯がたたない強力な陰の集団で、一般人の目に見えないところでずっと活動を続けてきた。世の中を好きなように動かせるだけの金と権力を手にいれなければ気がすまず、人が癌になったり、痛みに悶えたり、命を落としたりするのを見ても同情心を全く感じないだけでなく、むしろ喜びを感じるような、病的で危険な犯罪者たちの集団である。
翌年の暮れ、Dさんという名のロンドンに住むフランス人の女性がベルリンのわたしの自宅を訪ねてきた。まだ美大を卒業して間もない若い人だが、すでに二回、福島に数週間ずつ滞在したということで、撮ってきた写真を見せてくれた。それはカタストローフェを写したセンセーショナルな写真ではなく、未解決の問題を抱えながら生活している個々の人間の顔や、思い出のしみついたまま変貌した様々な場所の写真だった。Dさんは、この先十年の福島を撮りたいのだと言う。
2013年夏、Dさんがいわき市に住むTさんを紹介してくれて、その方の案内で、いわき市中央台の仮設で生活する方々と会うことができた。それから、いわき市の薄磯地区、富岡町上手岡、富岡町夜の森、楢葉町山田岡地区などをまわり、浪江町から避難している方々のお話も聞いた。喜多方に避難しているTさんの叔父さんを訪ねた帰りに三春にも寄った。三泊四日の短い滞在だったが、わたしはたくさんの方々から貴重なお話を聞かせていただき、感謝の念でいっぱいだった。
短編「不死の島」を展開させて長編小説を書くつもりだったわたしは、この旅をきっかけに立ち位置が少し変わり、その結果、『献灯使』という自分でも意外な作品ができあがった。
(たわだ・ようこ/小説家、詩人)

大災害により、自然も社会も取り返しのつかない損害を受けてしまったのちの物語である。日本は鎖国の道を選び、政府は民営化され、政治家は無益な法律改正にあけくれるばかり。子供たちは微熱が下がらず、ちゃんと立って歩くこともかなわない。皮肉にも、老人たちは壮健で力にあふれている。「死ねない身体を授かった」ことのつらさを抱えながら、自分たちより先に命が尽きるだろう若者たちの世話をするという定めを甘受している。
ご覧のとおり、表題作の設定には、わが国が抱え込んでいる難問の数々が取り込まれている。三・一一以降の状況に加え、少子高齢化とそれにともなうアポリアの数々が、鋭く映し出されている。ところがこの小説はわくわくと楽しく、弾むような愉快さに満ちているのである。そのことに心から驚かされる。ユートピアの正反対、まさにディストピア文学でしかありえないはずの条件がそろっているのに、〝呪い〟を軽やかに振り払うしなやかな語りが実現されている。読んでいて何だか元気になってくる。
そもそも小説の中では、ディストピア的状況それ自体がおかしさを帯び、笑いを生み出す。鎖国下、イギリスやフランスといった国名を口にすることさえ憚られる抑圧的環境の中で、百歳を超えてなお元気な作家の義郎(よしろう)は毎朝、土手をジョギングする。しかし外来語は廃れ、ジョギングは「駆け落ち」と名を変えている。駆ければ血圧が落ちるから、というのだから笑ってしまうし、脱力を誘われもする。強張ってしまいそうな心身の力みを解くすべが、閉塞状況を描き出す言葉のうちに含まれているのだ。
主要な視点人物となる義郎が、鎖国以前から書き続けているベテラン作家であることは、この小説のなかで文学に、そしてより具体的には文字に担わされた役割を際立たせている。文学者が反逆精神とともに立ちあがるという以上に、あるいはそれ以前に言葉自体が勝手に立ち上がり、ユーモアを漂わせもすれば、不穏な予兆をはらみもする。鎖国後新しく制定された休日のうちに、「インターネットがなくなった日を祝う『御婦裸淫の日』」なるものがある。カタカナ表記が抑圧されるとき、漢字はにわかに淫乱さを増すのか。そこには、カタカナ表記の消滅という事態と引きかえに、日本語が新たな表現と身体を見出すというプロセスが認められる。つまり文字や言葉のうちには、死んでもまたよみがえる力が宿っている。あるいは、意味の枠をはみ出してやろうという不埒な気配を、言葉はつねに秘めているともいえる。そこに文学創造にとっての根拠もある。
たとえば義郎は、「蓼」という漢字を書くたびに「文字を書くことの喜びに引き戻された」。〝ノノノ〟の部分が彼の官能を刺激するのだ。「爪で樹木の外皮をななめに引っ搔く猫科の動物の子供になったつもりで」、彼は「蓼」の字を書く。「猫科の動物の子供」という説明は見逃せない。動物になること、子供になることが重要なのである。ディストピアを生きる──しかも悦ばしく生きる──ための方途がそこに見出される。実際、この小説の中心には子供がいる。彼がいわば非人間化していくさまが、まさに一個の希望として輝き出す。
義郎がひとりで育てる曾孫、無名(むめい)。学校まで歩いていくこともできず、食べ物を咀嚼することもむずかしい。「昔の人は鳥の内臓や妊娠中の川魚を串に刺して直火で焼いて食べることもあったらしい」と驚嘆するこの男児は、いわば究極の草食系とでもいうべき風情だ。だが、いかにも惰弱な無名のふるまいや思考をとおして、何ともいえずやわらかでやさしい心身のあり方が示されていく。驚異の感覚に打たれずにはいられない。
朝起きて服を着ることがすでに、無名にとっては大変な格闘の一幕となる。寝間着を脱ごうとしてなかなか脱げず、通学用ズボンをはこうとしてまた難儀する。それは彼が「蛸」だからなのであり、着替えの際には余計な足がじゃまをしにかかるのだ。そのひと苦労を蛸のダンスとして活写する文章自体が、軟体動物的な弾みかただ。軟体動物は決してただぐにゃぐにゃしているだけではない。「これみよがしの筋肉」とは異なる無駄のない肉が無名の身体には張りめぐらされていき、義郎はそこに、これまでの人間の二本足歩行とはまったく異なる移動方法の可能性を垣間見る。
その動きは、従来の社会を縛ってきた価値観の枠外へとすべり出ていく精神のあり方と結びついている。無名はまったく無知であり、〝無明〟の闇にあるとも思える。だがそれは過去に囚われることがなく、自らを憐れんだり悲観したりする必要がないということでもある。ルサンチマンやメランコリーと無縁に、彼は日ごと、「めぐりくる度にみずみずしく楽し」い朝を享受する。声変わりはせず、男でも女でもなく、若くして白髪を戴き年齢の秩序をも攪乱する彼は、やがて海の闇に身を投じ、禁を犯して「世界」へ旅立つときを待つ。
ここには確かに「まだ到着していない時代の美しさ」が、その不思議なきらめきがとらえられているのを感じる。「百年以上の信念を疑う」必要に迫られたとき、進歩や退化の観念を逸脱して、未定形な生のあり方をのびやかに描き出すことができるなら、どんなにすばらしいだろう。それを多和田葉子は、言葉の秘めた変身可能性──いにしえの遣唐使は灯を献ずる使いとして生まれ変わる──への感応力を存分に発揮することによって、あざやかに実現してみせたのである。
同時に収録された四編も、表題作にさまざまな照明を投げかけて実に興味深い。そこでも、漢字はその内なるエロスを明かし、不死の老人たちは「永遠の青春」に耐え、政治家は懊悩し、動物たちは人間を糾弾している。眠れる恐竜( それともオオサンショウウオ?)の目覚めを描いた堀江栞による挿絵が、独特の生命感によって本書の味わいをいっそう深めていることも特筆しておきたい。
※この書評は単行本刊行時のものです。
1960年、東京生まれ。小説家、詩人。早稲田大学第一文学部卒業。ハンブルク大学修士課程修了。82年よりドイツに住み、日本語・ドイツ語両言語で作品を手がける。91年、「かかとを失くして」で群像新人文学賞受賞。93年、「犬婿入り」で芥川賞受賞。96年、ドイツ語での文学活動に対しシャミッソー文学賞を授与される。2000年、『ヒナギクのお茶の場合』で泉鏡花文学賞を受賞。同年、ドイツの永住権を取得。また、チューリッヒ大学博士課程修了。11年、『雪の練習生』で野間文芸賞、13年、『雲をつかむ話』で読売文学賞、芸術選奨文部科学大臣賞をそれぞれ受賞。18年、本書『献灯使』で全米図書賞(翻訳文学部門)受賞。近著に『百年の散歩』『地球にちりばめられて』がある。
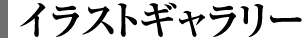
※画像の無断転載、使用は禁じられています。
堀江栞 / Horie Shiori 1992年生まれ 2014年 多摩美術大学 美術学部 絵画学科 日本画専攻卒業。 2015年 第26回五島記念文化賞 個展(アートフェア東京2015)